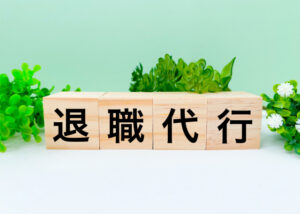賃金不払のトラブル 欠勤控除と賃金全額支払いの誤解
目次
飲食店で起こりやすい「賃金不払」トラブルの実態
飲食業界では、日々の売上や人員体制に応じてシフトを柔軟に組むことが多く、「働いた分だけ払う」という考え方が根付いています。
しかし、労働基準法上の「賃金の支払い」に関するルールを十分に理解せず、欠勤控除やシフト削減を誤った形で行ってしまうケースが少なくありません。
特にトラブルが多いのは、次のような場面です。
- スタッフが欠勤したときに「丸1日分の給与を引いたが、計算があいまい」
- 会社都合で労働時間を減らしたのに、勤務時間分しか払わなかった
- 遅刻・早退の控除を“その時間分”ではなく“勝手に半日分カット”
- 売上が少ない日を理由に勤務時間を短縮したが、給与をその分減らした
これらは一見「当然の対応」と思われがちですが、法的には“賃金不払い”に該当するリスクがあります。
実際、飲食店での賃金トラブルは全国の労働基準監督署でも多く見られます。
特に「全額払いの原則」を誤解していると、悪意がなくても違法状態になるのです。
「全額払いの原則」と「欠勤控除」の正しい関係
1. 賃金支払いの5原則とは
労働基準法第24条は、「賃金支払いの5原則」として、次のルールを定めています。
1️⃣ 通貨で支払うこと
2️⃣ 直接労働者に支払うこと
3️⃣ 全額を支払うこと
4️⃣ 毎月1回以上支払うこと
5️⃣ 一定の期日を定めて支払うこと
この中で誤解が多いのが、③全額払いの原則です。
「全額払う」といっても、必ずしも“予定していた給料の全額を無条件に払う”という意味ではありません。
労働した分は全額払わなければならないというのが本来の趣旨です。
2. 欠勤・遅刻・早退があった場合
労働基準法では、働かなかった時間分の賃金を支払わないこと(=欠勤控除)は認められています。
つまり「欠勤控除」そのものは違法ではありません。
ただし、注意すべきは計算方法と理由の明確化です。
勤務日数や時間が明確に管理されていないと、控除の根拠を説明できず「未払い扱い」とされるリスクがあります。
3. 会社都合で勤務がなくなった場合
ここが最も誤解が多いポイントです。
たとえば「今日はお客さんが少ないから帰っていい」と指示した場合、これは労働者の都合による欠勤ではなく、会社都合の休業です。
この場合、会社は平均賃金の6割以上の休業手当を支払わなければなりません(労働基準法第26条)。
つまり、
- 労働者が休んだ:欠勤控除OK
- 会社が休ませた:休業手当が必要
この違いを混同すると、思わぬ賃金不払トラブルになります。
よくある誤解と違法リスク
1. 「シフト減らしたから払わなくていい」は誤り
飲食店では、閑散期に「シフトカット」が発生することがあります。
ただし、これは雇用契約で労働日数・時間が定められているかどうかによって扱いが異なります。
- シフト希望制のアルバイト:出勤確定していない分は賃金発生しない
- 固定シフト・契約時間制:会社都合のカットは休業扱い
つまり、「働かせなかったのは誰の都合か」で判断されるのです。
2. 「遅刻したから1時間分×時給」でカット」も要注意
遅刻・早退による控除は、実際に労働していない時間分を正確に時間単位で差し引くのが原則です。
「10分遅刻したから1時間分カット」などは、過剰控除となり違法の可能性があります。
3. 「日給制だから欠勤日はゼロ」はOKか?
日給制であっても、実際に働いた日には全額支払う義務があります。
逆に、労働日以外の欠勤日を控除すること自体は問題ありませんが、
途中で退勤した場合に“1日分全カット”するのは行き過ぎです。
正確には、労働した分(例:3時間分)は支払わなければなりません。
4. 「お客さんが来ないから早上がり」も危険
飲食店では、状況に応じて早退を指示することが多いですが、これは会社の指示=休業手当が必要なケースに該当します。
特に、労働者本人が「早く帰りたい」と言っていない場合は注意です。
トラブルを防ぐための給与計算ルール設計
1. タイムカード・シフト表の一貫管理
労働時間の根拠を明確にすることが最も大切です。
シフト作成、出勤打刻、給与計算がそれぞれ別管理だと、証拠が食い違いトラブルのもとになります。
おすすめは、
- タイムカード(勤怠システム)で実労働時間を自動記録
- シフト表に「会社都合休業」「本人欠勤」などの区分を明記
- 給与明細に、控除理由を具体的に記載
こうすることで、後から「不払いだ」と言われても説明できます。
2. 欠勤控除のルールを就業規則に明記
「欠勤控除」や「遅刻早退控除」については、就業規則や雇用契約書に明記することが重要です。
書面でルール化されていないと、後で「勝手に引かれた」と主張される可能性があります。
【記載例】
第○条(欠勤控除)
労働者が欠勤、遅刻、早退した場合は、所定労働時間に応じて賃金を控除する。
3. 休業時の対応フローを決めておく
飲食業では天候・設備トラブル・感染症対応などで営業停止になる場合があります。
このとき、すぐに「休業手当を払うか否か」を判断できるよう、休業時マニュアルを整備しておくと安心です。
4. 管理者教育の重要性
現場責任者が「今日はお客さん少ないから早く帰って」と判断してしまうケースが多いです。
これは店長個人の判断であっても、会社の指示とみなされるため、休業手当が発生します。
したがって、店長・マネージャーには「早退指示=手当発生」のルールを教育しておく必要があります。
実際にあった相談事例と社労士からのアドバイス
事例1:シフトカットで給与が半分に…
繁忙期が終わり、週5勤務だったアルバイトを週2に減らしたが、本人から「急に減らされたのに給料も減った」と労基署に相談された。
→雇用契約で週5勤務を前提にしていた場合、会社都合の休業扱いとなり、休業手当の支払い義務があります。
シフト調整は本人の同意書を取ることがポイントです。
事例2:「お客様が少ないから今日は半日で」
店長判断で早退を指示。給与は実働分のみ支払い。
→労基署調査で「会社の指示による短縮」と判断され、休業手当の支払い命令。
現場判断でも、会社としての責任を問われます。
事例3:遅刻30分で1時間分カット
店長が「30分単位で切り上げ」として控除。本人から不満。
→30分の遅刻なら30分分のみ控除が原則。
“単位丸め”のルールは原則NG。正確な時間管理が必須です。
社労士からのアドバイス
- 欠勤控除は“適正計算”を行えば合法
- ただし、会社都合の勤務削減は不払いリスク大
- シフト削減や早上がりの際は、「本人希望か」「会社指示か」を記録に残す
- タイムカードと給与計算が一致しているか、常にチェック
まとめと当事務所からのサポート
「欠勤控除」と「全額払い原則」は、飲食業で最も誤解されやすいテーマの一つです。
“働いていない時間分を差し引く”ことは認められますが、それが誰の都合で発生したのかを正しく判断しないと、簡単に「賃金不払」へ発展します。
当事務所では、
- 就業規則・雇用契約書へのルール明文化
- シフト削減・休業時の適法対応マニュアル作成
- 現場店長向けの労務管理研修
など、実務に即したサポートを行っています。
✅「欠勤控除の扱いが正しいか不安」
✅「シフト削減でトラブルになりそう」
✅「休業手当の判断が難しい」
👉 お電話や お問い合わせフォーム から、お気軽にご相談ください。