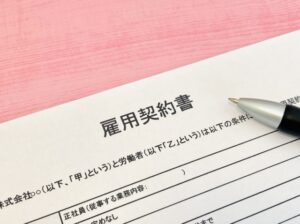【飲食業専門社労士が解説】無断欠勤・遅刻・早退が多発!“モチベーション低下”の真因と労務対応策
目次
無断欠勤・遅刻・早退が増える「本当の理由」
飲食店で「最近、スタッフがよく遅刻する」「連絡なしの欠勤が増えている」という声を多く聞きます。
実はこれ、単なる“怠け”ではなく、店舗運営や職場環境のシグナルであることが多いです。
よくある背景
- シフト過多・休憩不足による疲弊
- 店長や社員とのコミュニケーション不足
- メンタル不調(不安・不満・ストレス)
- 業務負荷の偏り(「できる人」に偏る)
- 店舗内トラブル(人間関係・指示系統)
社労士の視点からの注意点
無断欠勤や遅刻が頻発する職場では、すでに労働時間管理や職場風土に課題が潜んでいます。
これを“個人の問題”として処理すると、退職者が続出し、採用コストも増加します。
まずやるべき3つの分析ステップ
① 勤務実態の把握
- タイムカード・勤怠データを分析
- 残業・早退・欠勤のパターンを可視化
- 特定曜日・ポジション・上司との関連を確認
② コミュニケーションの現状確認
- 店長とスタッフの1on1ミーティング
- チャット・LINEグループのやりとり内容を再点検
- 「言いたいことを言えない」雰囲気がないか確認
③ 労働条件・シフト設計の再点検
- 休憩が実際に取れているか
- “週5日連勤”などの過重スケジュールがないか
- 短時間勤務者の希望と実勤務の差異を確認
改善のための具体的ステップ
ステップ①:勤務時間と休憩ルールの見直し
- 休憩を取らせる責任は会社側にある
- 忙しい時間帯を避けたシフト休憩制の導入
- 休憩未取得が続く場合は、シフト設計を再構築
ステップ②:シフトの“相談制”を導入
- 「固定シフト」から「希望申告+相談制」に
- 変更依頼ルールを明文化(例:前日までに申請)
- LINEやアプリで“確認・承認”の痕跡を残す運用
ステップ③:店長のマネジメント教育
- 感情的対応を避け、対話型マネジメントへ
- 叱責よりも「なぜ来れなかったのか」を聴く姿勢
- 勤怠不良を早期に察知する“声かけ文化”の育成
メンタルヘルスと職場コミュニケーション
メンタル不調を疑うサイン
- 無断欠勤が「連続」して起こる
- 店長との接触を避ける
- 連絡を“既読スルー”する
この場合、まずは産業保健的な配慮対応を行う必要があります。
小規模店舗では、店長自身が「初期対応者」となります。
労務上のポイント
- 欠勤連絡がない場合でも“安否確認”を必ず行う
- 3日以上の無断欠勤には書面での催告を
- 精神的な不調が疑われる場合は、医療機関受診を案内
- 一律処分ではなく、事情聴取と記録を残す
就業規則への落とし込み
無断欠勤や遅刻への対応を明文化することで、公平な処理と抑止力を両立できます。
記載例
第○条(無断欠勤・遅刻等)
- 正当な理由なく遅刻・早退・欠勤した場合は、懲戒の対象とする。
- 無断欠勤が3日以上に及んだ場合は、退職の意思表示があったものとみなし、自己都合退職として扱うことがある。
- 無断欠勤が発生した場合は、会社は安否確認のうえ、書面による通知を行う。
店舗としての予防策まとめ
- 勤怠の「見える化」(タイムカード+店長週報)
- 店長・社員の労務研修(パワハラ防止+勤怠管理)
- スタッフアンケートによる現場の声の吸い上げ
- モチベーション指標(シフト希望率、遅刻率など)の導入
当事務所からのアドバイス
無断欠勤・遅刻は“末期症状”です。
その前段階で「兆し」を察知し、仕組みで防ぐのが飲食店の労務管理の要です。
- シフト変更・欠勤ルールの設計
- 店長向けマネジメント研修
- 就業規則の再設計(懲戒・欠勤条項の見直し)
などを行っています。
現場を守るためのルール整備は、👉 お電話や お問い合わせフォーム から、お気軽にご相談ください。