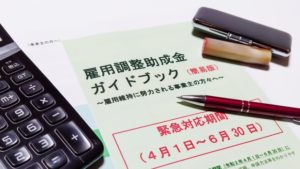法律を読み解くうえで、最低限知っておきたいこと
普段お生活ではあいまいに使っている言葉でも、条文を読むときには厳密なルールがあります。
休業手当の記事を書いたときに、条文で「以上」という用語について少し書きましたが、今日はもう少し掘り下げて書いてみたいと思います。
目次
以上、超えるなど
以上、以下の「以」には、もってという意味がありますので、含むという意味になります。
したがって、60日以下というと、60日を含んでそれ以下の日になります。
60日以上も60日を含んでそれ以上の日を指します。
超える未満は、以上などの逆でその数値を含まないです。
60日を超えるというと、61日以上になります。
60日未満であれば、59日以下になります。
以後、以降
これも「以」を含みますからその数値を含みます。
たとえば、退職日以後という場合は、退職日を含んで退職日から後の日になります。
退職日以降も、退職日を含みます。
以降も、以後と同じ意味なのですが、継続的にずっとというような意味合いも含みます。
推定する、みなす
推定するというのは、本当なのかどうかわからないけど、反対の証拠が出てこないなら一旦そうしましょうということです。
以下の条文は労災法の抜粋ですが、生死も定かではないけど、3か月も行方不明なんだから、死亡していると思うから、船舶が転覆等した日に死亡したことにします。
でも、生きていたら死亡は取り消します。ということです。
<労災法10条>
船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた労働者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた労働者の生死が三箇月間わからない場合又はこれらの労働者の死亡が三箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び葬祭給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日又は労働者が行方不明となつた日に、当該労働者は、死亡したものと推定する。
みなすは、本当かどうかわからないけど、反対の証拠があっても決めたことは変えないですということです。
以下の条文は、労基法の事業場外みなし時間の規定ですが、業務で外出したときに労働時間が何時間働いたかわからないときには、本当は違うかもしれませんけど、所定労働時間働いたことにしますよ。という意味です。
<労基法38の2>
労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。